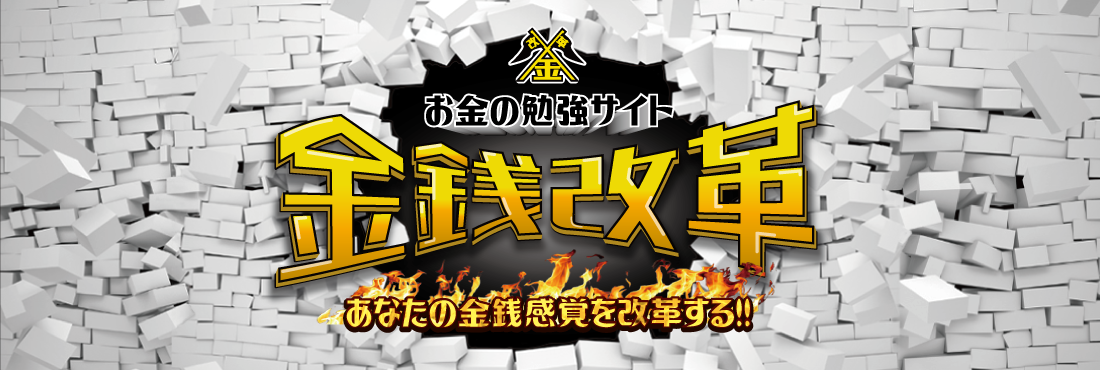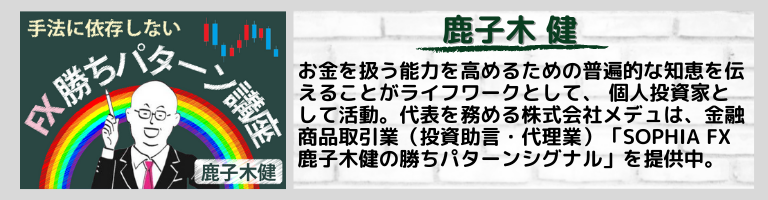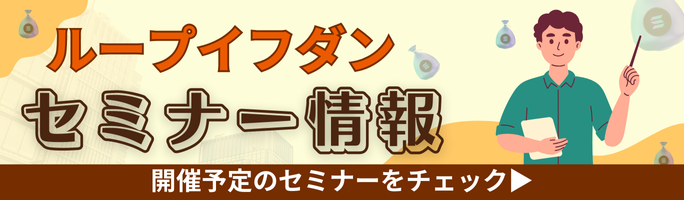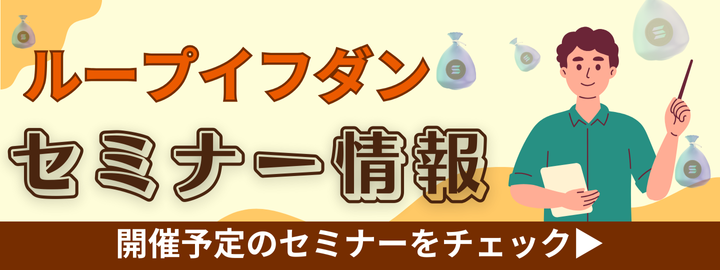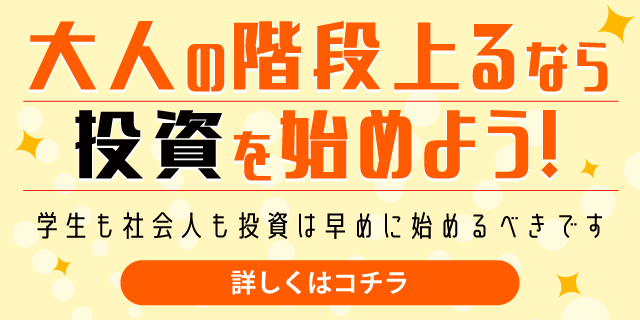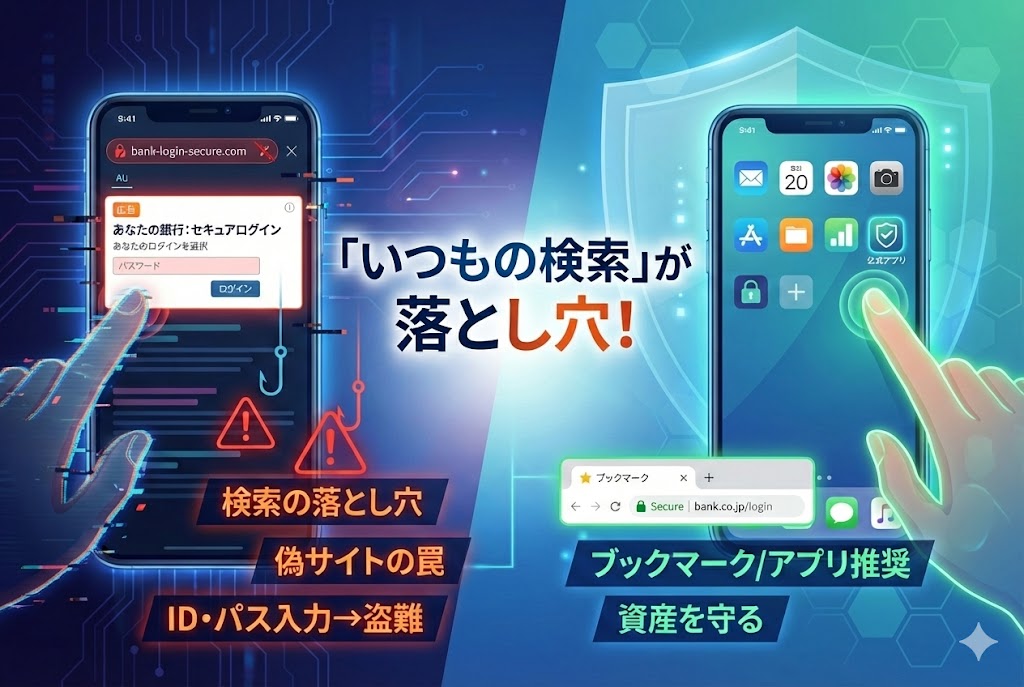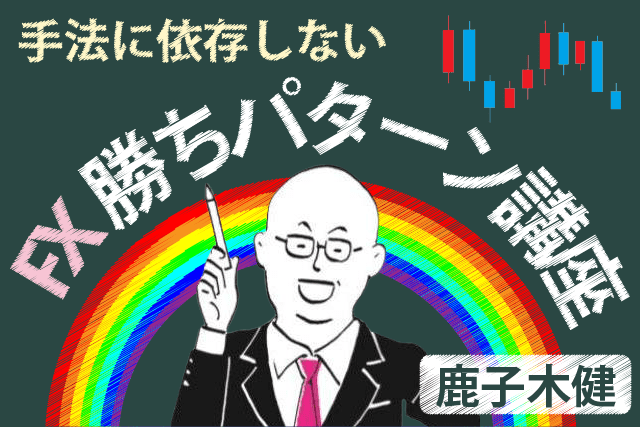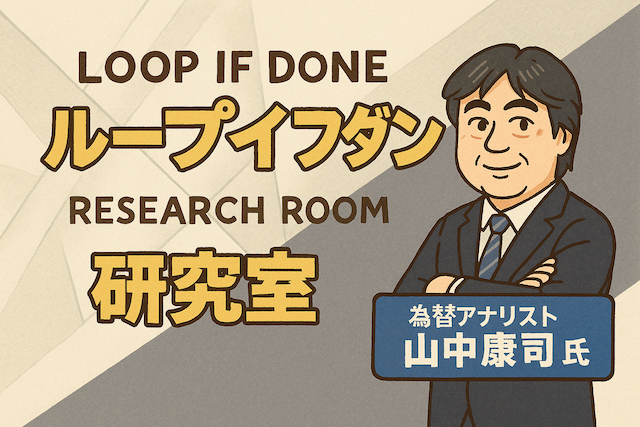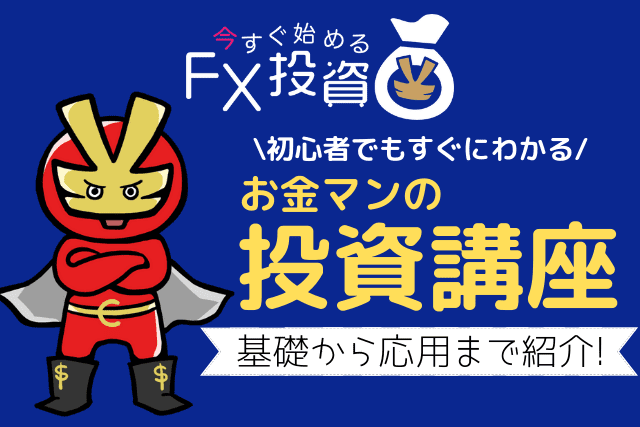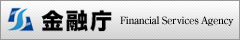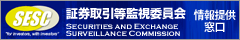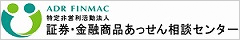このエリアにHTML要素を追加する
あなたが考えているほど長期目線の積立投資は簡単ではありません【鹿子木健】

最近は投資による資産形成が話題になっています。特に2024年からは新しいNISA制度が始まるためか、雑誌やSNSなどで「分散してリスクを抑えつつ、長期で積立投資をしていこう」という声が大きくなっているような気がします。
しかし、現実として、投資初心者には長期の積立投資は難しいです。その理由を解説していきます。
1.スタート時の投資環境によって大きくブレる
2024年から新NISAが始まりますが、それに伴って「投資で資産形成をしよう」という声が高まってきています。
特に、長期目線で積立投資をしていけば投資初心者でも利益を出しやすいという風潮が強まってきているように感じます。しかし、私としては、これらの言葉が独り歩きしているような気がします。
長期投資と積立投資の大前提は、株価は長期的には上昇していく可能性が高いので継続的に買っていけば将来的に利益を出せるという考え方です。これは反対に、長期的に下落する時は損失を抱えてしまう可能性があるということです。
日本のバブル景気を例に考えると分かりやすいです。日経平均株価は1989年12月に史上最高値の3万8915円をつけましたが、そこからは急落しています。
仮に最高値から長期で積立投資をしていた場合、計算上では2013年のアベノミクスで株価が上昇していくまで含み益にならない計算です。つまり、約25年もの間、積立投資を続けていないと損失を出してしまうということです。
相場が上がるか下がるかは誰にも読めません。バブル経済のように上昇を続けるかもしれませんし、2024年からは下落していく可能性もありえます。
そのため、20年や30年といったスパンでの運用を想定しておく必要があります。20代や30代の人が長期の積立投資をするのは意味があるかもしれませんが、50代や60代の高齢者寄りだと、含み損のまま終わる可能性も考慮する必要があると思われます。
一方の分散投資のメリットは、リスクヘッジができることです。ただ、業種だけを分散させて全て日本株という投資方法では、バブル崩壊のような日本株全般が下落した際に大きなダメージを受けてしまうため、この点には注意が必要です。
2.長期で続けられるメンタルを持っているか
ここまでの説明で、20代や30代から始めれば長期保有ができるのでメリットがあると思われるかもしれません。
しかし、現実的に考えると「そもそも投資を続けられるのか」という大きな問題点があります。
投資の大原則として、相場はずっと上がり続けるわけではありません。1年や2年というスパンで下落することもあれば、場合によってはバブル崩壊後の日本株のように10年スパンで低迷することもあります。
仮に積立投資を始めたところから下落し、将来の相場が上がるか下がるかが全く分からない状況の中で、「いずれ上がるだろう」と買い続けられる人はどのくらいいるのでしょうか。
相場にはサイクルがあり、いつかは上昇していきます。しかし、実際に低迷している相場状況やチャートを目の当たりにして「いつかは上昇していく」と買い続けられる人は投資を理解し、ある程度の経験を積んでいる人だと思います。
私は、投資初心者で相場が低迷している中で買い続けられる人は少ないと思います。
3.長期の積立投資は難しいということを理解しておくべき
「積立投資で資産形成をしよう」のように、長期積立投資をお勧めする書籍は多々あります。さらに、昨今ではYouTubeやSNSでも「S&P500を積立てて長期投資をしよう」のような内容も多いです。
これらは投資初心者向けと銘打っていることが多いですが、現実の相場において、長期の積立投資をしていくのは初心者にはかなり難しいです。
しかも、話題性重視のためか、株価が上昇を続け、株式投資に湧き上がっている時に長期の積立投資を勧めてきます。
長期の積立投資は、株価が低迷している時こそ一番優位性を発揮できるということは絶対に頭に入れておいてください。
【注意事項】
- 本レポートは筆者の主観及び経験に基づき執筆されており、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。筆者及び株式会社アイネット証券は、本レポートの利用あるいは取引により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。
- 本レポートはあくまでも参考情報であり、筆者及び株式会社アイネット証券は、為替やいかなる金融商品の売買を勧めるものではありません。取引を行う際はリスクを熟知した上、完全なる自己責任において行ってください。
- 当コラムにてループイフダンの実績を紹介する際に使われている「年利」は元金に対する年間の利益率を指しており、金利や利息を指すものではありません。
- 筆者及び株式会社アイネット証券の許可無く当レポートの全部もしくは一部の転送、複製、転用、検索可能システムへの保存はご遠慮ください。