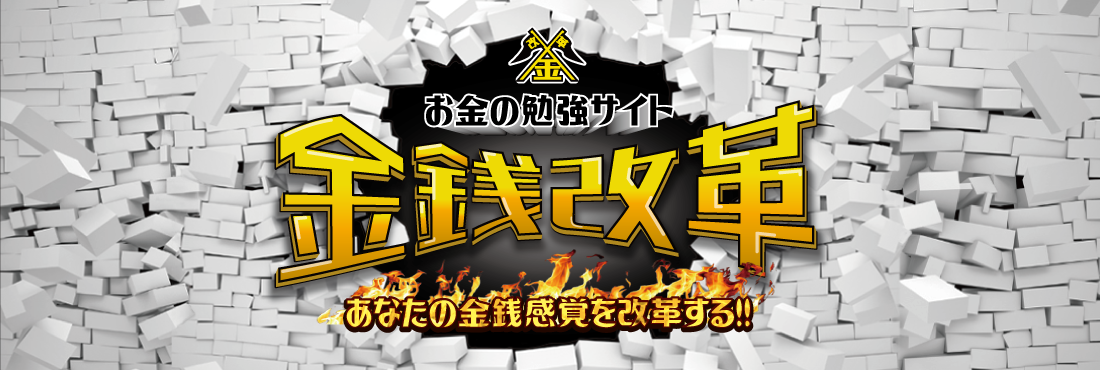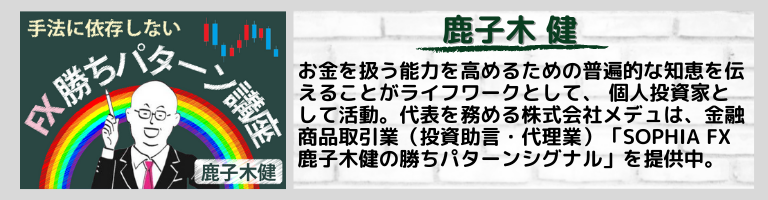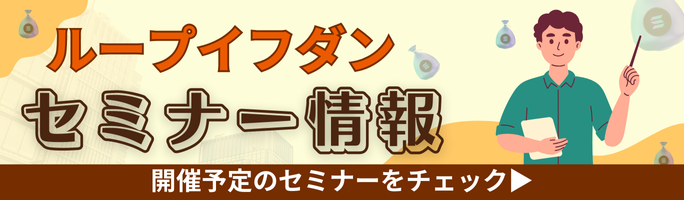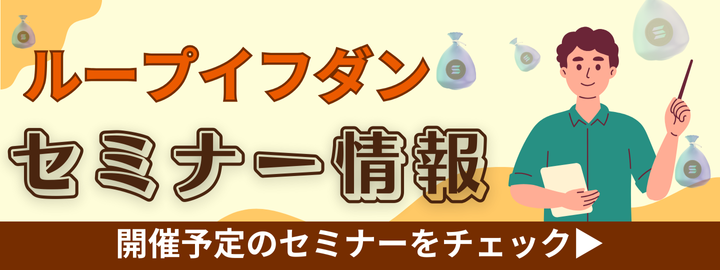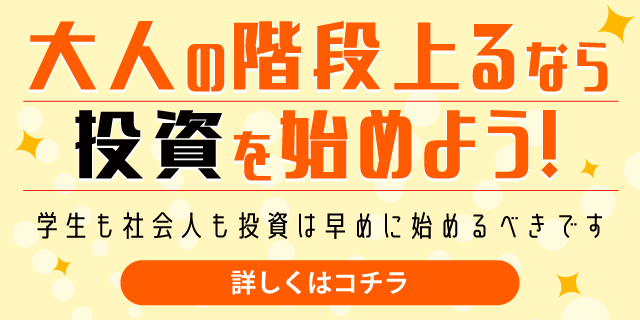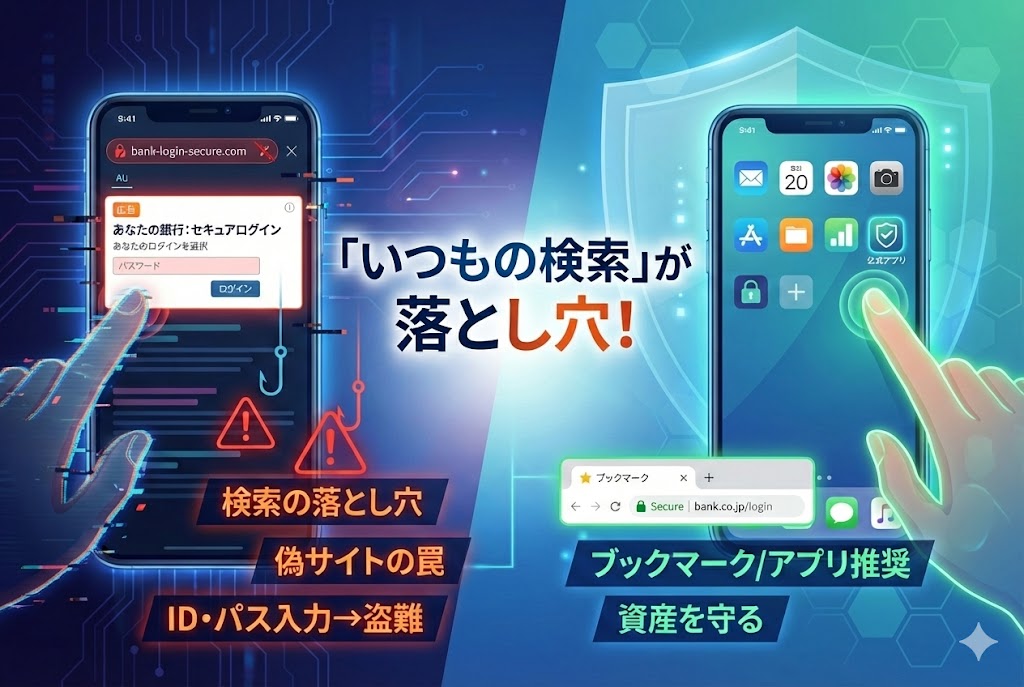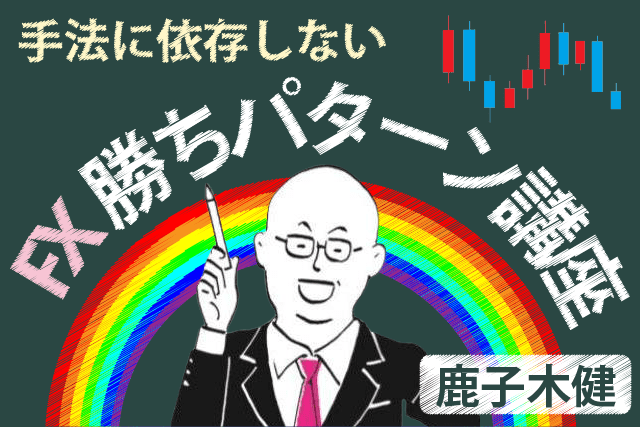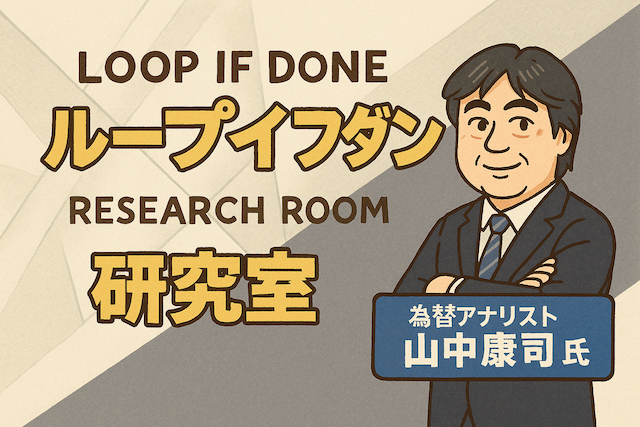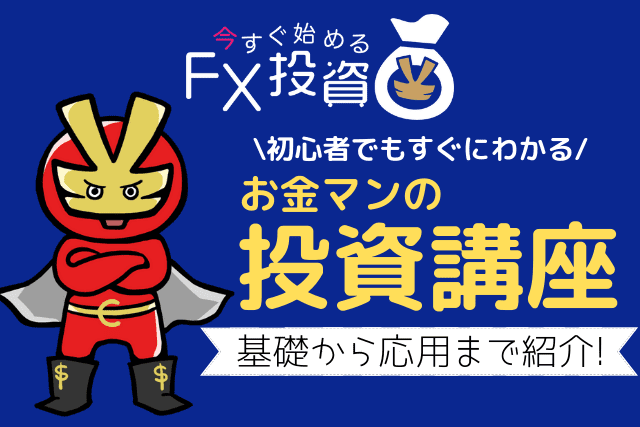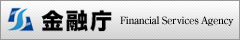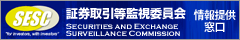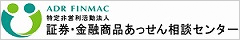このエリアにHTML要素を追加する
4つの段階を区別して投資しましょう【鹿子木健】

投資と一言でいっても、投資にはさまざまな段階(領域)があり、「投資は〇〇だ」と単純に言い切ることはできません。4段階に分けると以下のようになります。
1 資産構築
2 資産運用
3 資産防衛
4 資産形成
これらの領域はこの順序通りではないケースもありますが、それぞれを区別して考える必要があります。こうした領域の区別があいまいなままだと、目的と手段が合致しなかったり、投資をした結果がうまく得られないこともあります。
図表:投資の4つの段階(領域)

今回は、「投資の4段階」についてお話しします。
1.作って増やす――資産構築と資産運用
資産構築は、最初の資産を作ることです。金額に決まりはなく、自分が資産だと認めれば、20万円でも資産になります。その資金を資産と考える人は、20万円を元に投資で成功しようと行動を起こすでしょう。
10万円でも、100万円でも、自分にとって必要な最初の資産をゼロから作ることが資産構築です。労働収入や、支出を減らして得た余剰資金などが、資産構築の主な手段となります。
資産運用は、先ほど資産構築で作った資産や、現在自分が保有している資産を増やしていくことです。金融商品などで利益を出しつつ、毎年複利で増やしていくのが主な手段となります。
資産運用にはリスクがつきものです。利益を得て資産を増やせる年もありますが、当然そうでない年もあります。資産運用でうまくいかない人の多くには、運用と構築の区別がついていないことが多いように感じています。
資産運用は、ゼロから資産を作ることではなく「さらに増やす」ことを指します。そのためには「安定」と「長期」の2つの要素が不可欠です。保有している財産を「守りながら増やしていく」必要があるわけですね。
ですから、短期で爆勝ちして利益を上げたとしても、長期的にその利益がなくなってしまっては、資産運用が成功しているとはいえないのです。
「安定」「長期」の要素を満たすためには、長期的な視点と、資産を分散させる考え方も活用していきます。そこで、資産防衛の概念が登場します。
2.守って巡らせる――資産防衛と資産形成
資産防衛は、その字のごとく、増やすことよりも「守る」ことに重心を置く行為です。ここでは「資産はお金だけではない」という考え方が重要になってきます。
金融資産や不動産はもちろんですが、心身の健康や才能、人間関係、教育なども資産となります。お金が残ってもお金以外が残らなかったら、それは資産を防衛できたことにはなりません。
また、インフレ対策、通貨安対策、相続対策や税金対策も、資産防衛に含まれます。資産防衛とは、人生の全領域が豊かになることとおおむね等しいといえるでしょう。
資産形成は、ここまで出てきた資産の構築、運用、防衛を統合した考え方です。過去から未来に向けて、「資産を生み、育て、成熟させ、他の勝ちを生み出す貢献をさせるサイクル」です。
資産形成の一環として資産を構築し、資産を運用し、資産を防衛するのです。資産形成は数年単位で考えるものではなく、一生かけて実践していくものです。子どもの世代にも引き継ぐことを考えたら、二代、三代と家を存続させることも資産形成になります。
3.もう一つのサイクル「増やす・使う・守る・承継する」
先ほど投資の4つの段階を説明してきましたが、もう一つ、大事なサイクルがあります。「増やす・使う・守る・承継する」の4サイクルです。増やす以外の3つのサイクルについては見落とされがちなので注意が必要です。
例えば農作物の栽培は、植えて、肥料をやって、水をやって育てます。育てた農作物は収穫が必要です。そうしないと、次の作物を植えて育てることができません。これが「使う」にあたります。
そして、農作物は干ばつや水害、あるいは盗難から「守る」必要があります。さらに、収穫した作物で終わりではなく、種として残し、次の世代が実らせることができるよう「承継」する必要があります。
これを資産に置き換えると、次への先行投資や社会貢献、人材育成のために「使う」ことや、適切なリスク管理や資金管理をして「守る」ことや、配偶者、家族、次の世代の若者たちへ「承継する」ことになります。
資産は生かされてこそ資産、次へ受け継がれてこそ資産です。先ほども申し上げた通り、資産はお金だけを指さないということを、折に触れて思い出していただければと思います。
【注意事項】
- 本記事に掲載する情報については、正確性・完全性の確保に努めておりますが、その内容を保証するものではありません。
- 本記事は、資産運用やFX取引に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の取引手法やサービスの利用を推奨・勧誘するものではありません。
- 投資に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
なお、本記事の閲覧または利用により生じたいかなる損害についても、著者および株式会社アイネット証券は一切の責任を負いかねます。