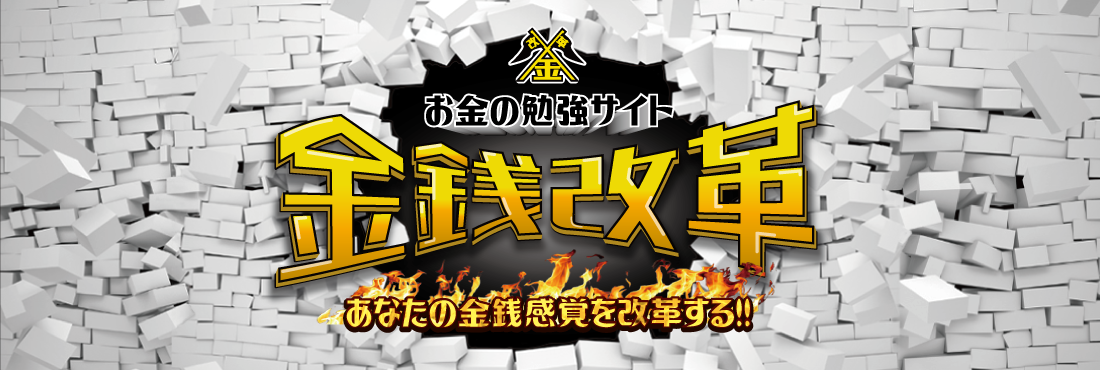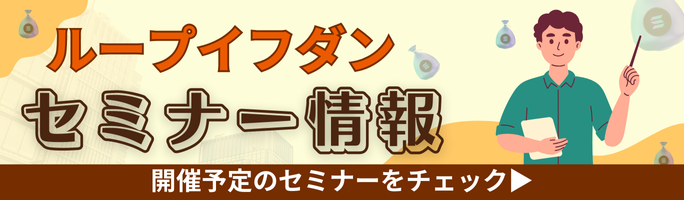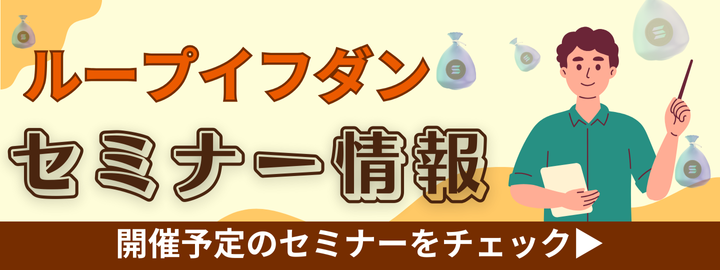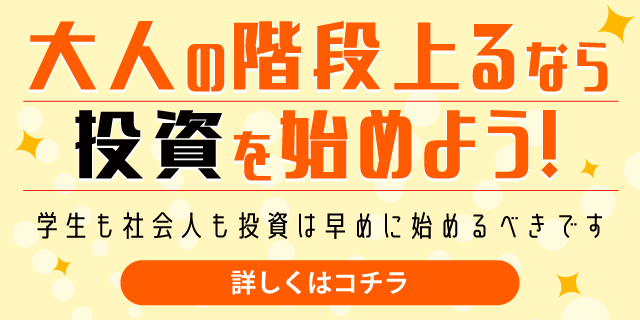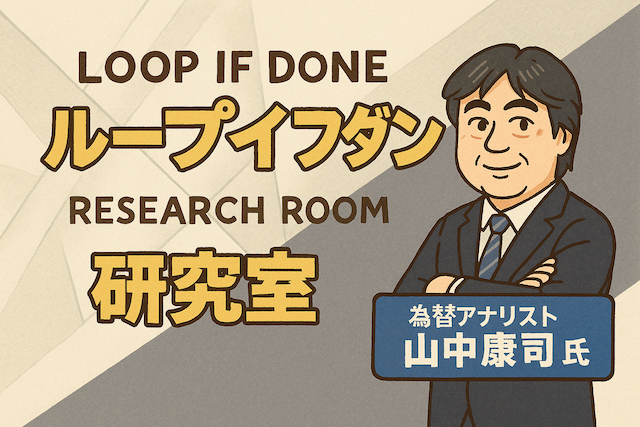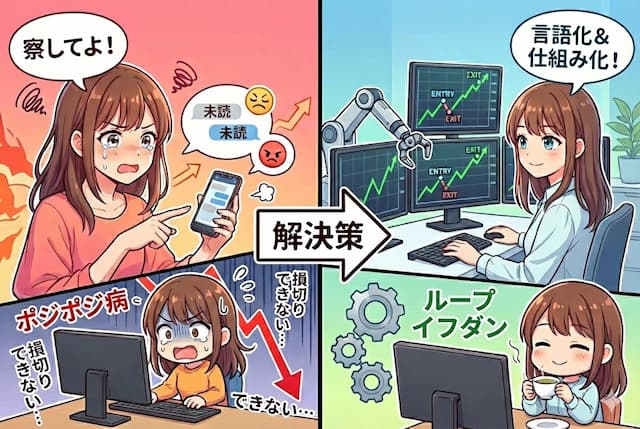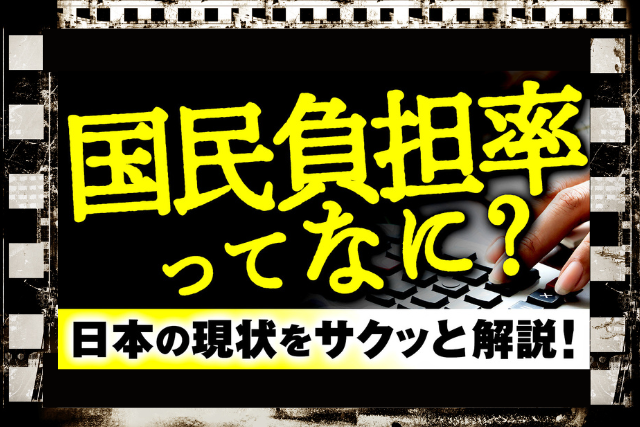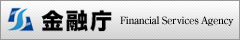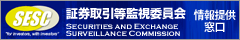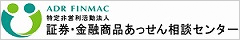【解説】定額減税は不評!?その理由や仕組み、対象者や手続きまでご紹介します!
2024年6月から、所得税と住民税の「定額減税」が始まりました。
今回の定額減税では、所得税で3万円、住民税で1万円、合わせて1人4万円の控除が行われます。
しかし、どんな仕組みなのか、実はよく理解できていないという方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、定額減税についてわかりやすくまとめてみました。
ぜひ最後までご覧ください。
なぜ定額減税が実施されるの?
冒頭でお話ししたように、
今回の定額減税は、国税の所得税と、地方税の住民税を合わせて、1人4万円が減税されます。
しかし、なぜ政府は定額減税の実施に踏み切ったのでしょうか?
その理由は、日本経済が「デフレ」に戻らないよう所得の伸びが物価の上昇を上回る状況をつくり、
デフレマインドの払しょくと好循環を実現するためとされています。
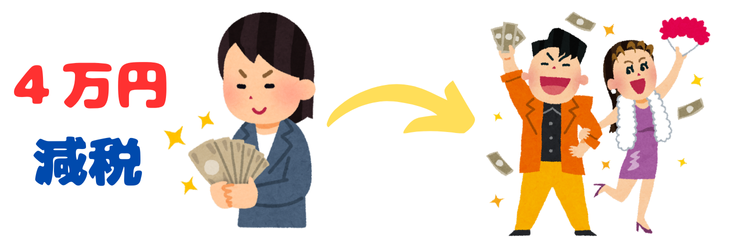
ですが現在、日本ではガソリンや食料品など、さまざまなものが高騰しています。
この物価上昇の状況を打破すべく、
2024年の春闘では、物価上昇に負けない賃上げの方針が打ち出されましたが
依然として実質賃金は25ヶ月連続マイナスと、プラスへの転換はいまだ見通せない状況が続いています。
このままでは、現在の物価高騰に賃金が追いつかず、生活が苦しくなってしまう世帯が増加してしま
います。
そこで、政府は、税負担を一時的に軽減することで
物価上昇による生活への影響を少なくしようと、今回の定額減税実施に踏み切ったのです。
定額減税の仕組みについて知ろう
そんな政府肝いりの定額減税ですが、その仕組みについても詳しくみていきましょう。
私たちが知っておきたいポイントは3つあります。
1つ目のポイントは、定額減税の対象者です。
控除が受けられるのは、令和6年に所得税と住民税を納税している人で、合計所得金額が1,805万円以下の個人です。
ただし、給与所得のみの方は、合計所得金額が2,000万円以下であれば対象となります。
2つ目のポイントは、ご家族の扱いです。
配偶者がいる場合、扶養に入っていなければ納税者本人として定額減税が受けられます。
扶養家族が複数いる場合には、その人数×4万円が定額減税の金額に加算されます。

3つ目のポイントは、
・会社から給料を得ている給与所得者
・個人事業主やフリーランスなどの事業所得者
・年金所得者
で、控除される金額は同じであるものの、控除のされ方が異なる点です。
給与所得者の場合、
所得税は2024年6月の徴収分から3万円が減額されます。
もし6月だけで3万円満額を減税できない場合には、7月以降から引かれることになります。
住民税については、2024年6月分は徴収されず、2024年7月から2025年5月までの11か月間、
本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し徴収されることとなります。
いずれも、定額減税を受けるために特別な手続きは不要です。
次に、事業所得者の場合、
所得税は予定納税がある場合、2024年7月の第一期から減税されます。
もし7月だけで3万円を減税できない場合には、11月の第二期に減税となります。
予定納税がない方は、確定申告時に減税が可能です。
住民税については、2024年6月の徴収分から1万円が減税されます。
6月分だけで減税できない場合には、8月分やそれ以降で減税されることになります。
事業所得者の場合は、住民税の定額減税を受けるための特別な手続きは不要ですが、所得税の減税には確定申告が必要です。
最後に、年金所得者の場合、
所得税は2024年6月の徴収分から3万円が減額
6月分だけで減税できない場合には、8月分やそれ以降で減税されます。
住民税については、2024年10月の徴収分から1万円が減税されます。
10月分だけで減税できない場合は、12月分やそれ以降で減税されます。
所得税、住民税いずれも、定額減税を受けるために特別な手続きは不要です。
ちなみに、住民税非課税世帯の方は、今回の定額減税は対象外です。
ただし、定額減税にかわる支援策として、給付金の支給が発表されていますので、
対象となる方は市区町村からの案内を確認するようにしましょう。
定額減税は増税を隠すためのまやかし?
さて、今回の定額減税は3人世帯でしたら12万円。ありがたいですよね。
ですが定額減税がはじまると同時に今年6月から、国民の負担は政府の増税などで大幅に増える見通しです。
その為、定額減税はそうした負担を覆い隠すための「まやかし」だとの批判もあります。
実際、物価高騰や政府による増税、社会保険料アップによる家計の負担は、
定額減税の金額を上回るのではとの試算がSNSなどで話題です。
その主張は、
「物価高騰対策」として2023年1月から行なわれていた電気代、ガス代の補助が、2024年5月で打ち切
られました。
これにより、標準的な世帯の一月あたりの電気消費量400キロワット、ガス消費量30立方メートルに、再エネ賦課金の引き上げを考慮すると、年間の電気・ガス代は3万2232円の負担増となります。
また2024年の春闘で、平均5.17%とかつてない賃上げの動きを維持していますが、
物価の上昇を考慮した「実質賃金」は依然としてマイナス推移が続いているため、
名目賃金が上がることで増えるのは税金と社会保険料の負担だけです。
ボーナス4か月支給の年収500万円のサラリーマンのケースでは、春闘どおりの賃上げが実現すれ
ば、年金、医療、介護の保険料は年3万5856円の負担増となります。
さらに、ガソリン補助金が2025年に打ち切りになりました。
ガソリン補助金の仕組みは複雑ですが、総務省によると2人以上世帯の年間ガソリン購入量は近年430L前後となっていて、補助金が打ち切られると一世帯の負担増は年6465円と小さくありません。
そのほか、2024年から住民税に1人1000円が上乗せされる「森林環境税」、医療費の窓口負担増など、もろもろ、増税のラッシュが続きます。

これらを総合すると、3人世帯の負担増は年間で約13万円、
定額減税12万円の恩恵はすべて打ち消されるばかりか、むしろ1万円の負担増になるのです。
もちろん、これはあくまで1つの試算です。
しかし定額減税は、電気代、ガス代の補助が打ち切られ、国民の負担が増す2024年6月から始まりま
した。
政府が定額減税に求める役割は国民の負担を減らすことではなく、
「ただ増える負担をカモフラージュしたいだけでは?」
「増税イメージを取り払いたいのでは?」
と言いたくなる方も少なくないのではないでしょうか。
定額減税をきっかけに、本当の意味で国民が安心して消費し、
潤った企業が賃上げで私たちに還元するという好循環は果たして実現するのか、今後の動向に注目したいところですね。
まとめ
今回は、2024年6月から実施される定額減税について解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしておきましょう。
定額減税は、2024年6月から、所得税で3万円、個人住民税で1万円、合わせて4万円が減税されます。
基本的には、特別な手続きは不要で、
対象者は、合計所得金額が1,805万円以下、給与所得のみの場合は2,000万円を超えない個人です。
また、扶養家族がいる場合、1人当たり4万円の控除が加算されます。
定額減税は、国民の可処分所得を下支えしてくれる支援策です。
今後増税ラッシュが続く見込みの我が国で、
30年振りとも言える賃上げの動きを加速させる起爆剤となるのか、注目です。
もちろん、私たち個人で堅実な投資を始め、
資産運用で賢くお金を増やす自助努力も大切です。
※この記事は2024年7月に執筆したものを2025年1月に編集しました。
ループイフダンお役立ちコンテンツ
ループイフダンの仕組み
いまいち 取引の仕組みがわからない・・・なんてお悩みじゃありませんか ? 運用開始時、相場上昇時、相場下落時、レンジ相場、相場動向にあわせてループイフダンの動きを紹介 します。
ループイフダン目安資金表
どれくらいの資金で運用できるんだろう?通貨ペアの過去のレートの変動はどれ位あったんだろう?最近人気の売買システムは?
ループイフダンの資金管理に必要な情報が満載です。
ループイフダン資金管理のコツ
資金にあわない無理な設定では、すぐに損切りやロスカットの憂き目にあってしまいます。
これから運用をスタートする2人を参考に 資金管理 のコツ を学びましょう。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。本記事の情報により生じたいかなる損害についても弊社及び執筆者は一切の責任を負いかねます。